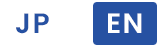<ガマカツ>新製品情報:LUXXE 宵姫 天
2018.04.06
CATEGORY カテゴリ
NEW POST 最新記事
- 『RYUGI』ブース情報
- 『HAL』ブース情報
- 『バレーヒル』限定販売品情報
- 【平谷湖フィッシングスポット】ブース情報
- 『SDGマリン/ミサイルベイツ』限定販売品情報
- 『RYUGI』ブース情報
- 『タナジグ』ブース情報
- 『RADSENSE』限定販売品情報
- 『DAIWA』ブース情報
- 『ZAPPU』限定販売品情報
- 『LINHA』ブース情報
- 『RAID JAPAN』ブース情報
- 『愛眼ストームライダー』限定販売品情報
- 『mode B』限定販売品情報
- 『CaptainSquid』限定販売品情報
- 『アングラーズシステム』限定販売品情報
- 『NISHINE LURE WORKS』限定販売品情報
- 『Dranckrazy』限定販売品情報
- 『パラドックス』限定販売品情報
- 『ヴァルケイン』限定販売品情報
CALENDAR カレンダー
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||

究極の「反響感度」「抵抗感度」「接触感度」の実現と軽量化のため、必要最低限のマテリアルで構成。ブランクスはもちろん、グリップレス構造など思い切った重量削減を導入し軽量化を図る。
ジグヘッドリグでの釣りのゲーム性を究極まで追求。
思い通りに操作し、狙って掛ける爽快感が味わえるスペシャルモデルです。
軽量ジグヘッドリグでのゲームを極める為に生まれたスペシャルスペックロッド2アイテム。
S54FL-solid
1g未満のジグヘッドリグを駆使したアプローチを極めるスーパーフィネスモデル。操作性とレスポンスを優先したショートレングスに設定し、ナノシェイクなど極めて細やかな操作が可能。わずかな荷重変化を感じることができる超センシティブティップにより引き抵抗、ルアーポジションを把握しながらの確実なルアー操作が可能となりました。ルアーを吸い込んだ瞬間の僅かなアタリを捉えることができるのはもちろん、水流変化、ジグヘッドリグの着底感度やリグの近くに寄って来た魚の波動をも捉えます。魚の気配というべき違和感までも 反響的シグナルとしてとらえることが可能な超微波動感知ロッドです。
S511FL-solid
1g前後のジグヘッドリグを駆使したアプローチを極めるモデル。リールシートポジションをエンド部に配することで得られるダイレクトな引き感をより大きく感じるためのレングスに設定。荷重変化を把握しながらの操作性に優れています。潮流が絡むエリアや水深があるポイントなどラインに水圧が掛る状況でもキレのある動きを演出できるレスポンスを備えつつ、反響感度とともに細かな変化を感じ取れるセンシティブな部分を共存させた設計です。
(1)リアグリップを排し、エンド部にリールシートを取り付けること(ワンハンド構造)でロッドレングスに対して最大の引き感を得られます。同時に素管エンド部に現れる反響的シグナルをダイレクトに感じとれます。
(2)オリジナル極薄高弾性カーボンパイプリールシートを採用することで、反響感度がよりクリアにまた微弱なシグナルも感じ取れます。
(3)小口径チタンフレームトルザイトリングガイドの採用(TOPガイドのみSIC)。その他部品類も必要最低限にまとめました。また、ブランクスもネーム部分以外は未研磨無塗装に仕上げ、これらによりトータルの感度UP、軽量化に成功しました。
(4)ガイドスレッドを巻く長さや、ラッピングの塗膜の厚さも軽量化の為に最適化しました。
(5)感度を最大限に出す為に、アーバーの素材・位置を試行錯誤の上、最高の状態にセッティングしました。
■付属のエンドキャップについて
※フィールドでリールを付けた状態で置く時やロッドホルダーに立てかける時、移動時や収納時に装着するグリップカバーです。
装着したままで釣りをした場合、ロッド本体が抜ける可能性があります。
必ず外してご使用ください。
■ワンハンド構造について・・・
●S54FL-solidのロッドの有効レングス(リールシートからティップまでの長さ)は通常のロッドの5’7″~5’8″相当となります。
●軽量ジグヘッドリグ単体使用が前提というパワー設定のモデルなので、リアグリップが無くても問題ありません。また上記の様にその方が感度が上がります。また、リールを持つ手より、エンド部を軽く触れる方が水中からの様々な情報を感知しやすいことから、その感度を最も得られる部分にリールシートを付けるという発想にいきつきました。
それにより、荷重変化を最大限に感じつつ、指先で触る感度に近い接触感度も向上しました。
●荷重変化を最大限に感じる事が可能になりました。